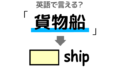電車やバスの【つり革】は英語で何て言う?

「つり革」は英語で【strap】
電車やバスなどの交通機関に備え付けられていて、走行時の振動や遠心力で転んだりしないように乗客が捕まる「つり革」は英語で[strap]などと表現します。
日本で「ストラップ」と言えば、スマホや携帯電話などにつけるひも状のものというイメージがあるので、丸や三角などの取っ手のついたつり革とは少しイメージが違いますよね?
海外の電車やバスに乗ると、平たいヒモが輪っか状にまとまっただけのつり革を見る機会も多いので「ストラップ:strap」という名前にもあまり違和感を感じないかもしれません。
例文として、「つり革や手すりにおつかまり下さい。」は英語で[Please hold on to the strap or handrail.]などと言えばオッケーです。
この例文のように「つり革につかまる」は英語で[hold on to a strap]と表現するのが一般的で、[hold a strap]とは言いません。
例に挙げた[hold ~]では「~を持つ」という意味になり、対象物が動いてしまうのに対して、[hold on to ~]は対象物が動かずに固定されていてしっかり「つかまる」という意味の違いがあるんですね。
他にも、「つり革」の英語として、手で捕まる場所である事がわかりやすい[hand strap]と表現する場合もあるので覚えておきましょう。
合わせて、つり革につかまってないと危ない【急ブレーキは英語で何て言う?】をチェック!